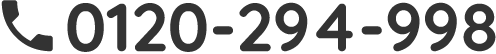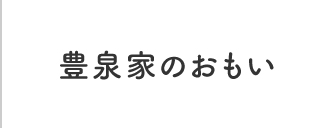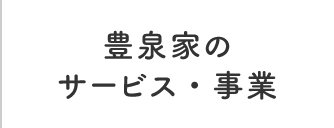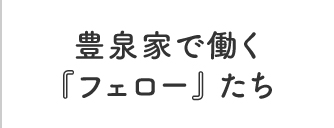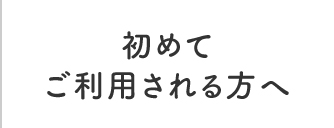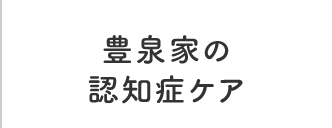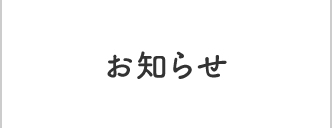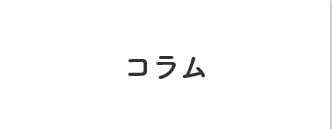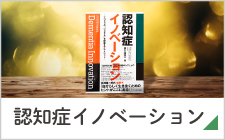認知症介護の5つの原則と心の負担を軽減する方法
2023.05.25
認知症ケア
認知症介護の5つの原則と心の負担を軽減する方法
認知症介護の5つの原則と心の負担を軽減する方法
認知症とは脳の認知機能低下により、日常生活にさまざまな支障が出る状態のことです。認知症の主な症状には記憶障害や見当識障害があり、症状が進行すると家族が誰かを思い出せなくなったり、性格が変化したりするケースもあります。
高齢者の家族が認知症になったとき、どのように介護すればよいかを知りたい人は多いでしょう。当記事では認知症介護をする人に向けて、認知症介護をするときに押さえたい5つの原則と、介護者本人が心の負担を軽減する方法を解説します。
目次
- 1.認知症介護をする家族の抱える思いとは?
- 2.認知症介護をするときの「5つの原則」
- 2-1.本人のペースに合わせてゆっくりを心がける
- 2-2.リアクションを大きく取ってコミュニケーションする
- 2-3.相手の気持ちに共感する
- 2-4.妄想は否定せず原因を探る
- 2-5.よい感情が残るよう前向きな言葉をかける
- 3.認知症介護をする家族の心の負担を軽減する方法
1.認知症介護をする家族の抱える思いとは?

認知症患者が見せる症状や性格・行動の変化に対して、認知症介護をする家族は下記のような思いを抱えることがあります。
- 「以前の性格とは変わってしまった」
- 「健康だった頃に戻ってほしい」
- 「本当は他に病気があって悪くなったのではないか」
- 「なんで認知症になったのだろう」
- 「どのように接すればよいか分からない」
家族が認知症になったとき、否定的な感情を抱えることは当然の反応です。しかし、戸惑いや混乱といった感情は、認知症になった本人も抱えていることを忘れないであげてください。
最初のうちは認知症に対して複雑な思いを抱えていても、家族が認知症になったことを受け止められる時期がやがて来るでしょう。認知症になったことを受け止め、症状も受容できるようになると、心が軽くなる可能性があります。
認知症介護をする家族は、いつかは認知症を受容できる時期が来ると胸に留めておくことが大切です。
2.認知症介護をするときの「5つの原則」

認知症介護をするときは認知症の症状を理解しておくと、日々を円滑に過ごせる可能性があります。本人が認知症で何も分からないとは考えず、人として尊重して向き合いましょう。
認知症介護をするときの「5つの原則」と、それぞれで意識すべきポイントを紹介します。
2-1.本人のペースに合わせてゆっくりを心がける
認知症になると脳の情報処理能力が低下して、一度にできることが少なくなったり、1つの動作に時間がかかったりします。介護をしていて歯がゆく思うことがあっても、急かすことは避けてください。
日常生活の動作に支障が出ていても、本人は自分でできることを精一杯やろうとしています。もしも急かしてしまえば、限界以上にがんばろうとして疲れてしまい、心を閉ざしてしまう可能性もあります。
認知症介護をする家族は、会話や動作を本人のペースに合わせることが大切です。会話や動作をゆっくりと行うことで、認知症患者が周囲の状況を理解しやすくなる可能性があります。
2-2.リアクションを大きく取ってコミュニケーションする
認知症介護をするときは、声や身振りのリアクションを大きく取ってコミュニケーションすることが大切です。
認知症患者は、言葉だけを使用する言語的コミュニケーションよりも、身振り手振りで伝える非言語的コミュニケーションのほうが理解しやすい傾向があります。非言語的コミュニケーションのポイントを押さえて、スムーズな意思疎通ができるようにしましょう。
たとえば安心させたいときは、相手と目線の高さを合わせてやさしく手を握ったり、肩をさすったりしてください。会話をするときは声の抑揚やうなずく動作を意識して、気持ちを伝えやすくするケアがおすすめです。
2-3.相手の気持ちに共感する
認知症患者は、認知症になる前よりも相手の感情を敏感に感じ取りやすい傾向があります。認知症介護でコミュニケーションを取るときは、相手の気持ちに共感して、感情を合わせられるようにしましょう。
たとえば認知症の家族が何かに対して悲しんでいるときは、「悲しいですね」と相手の感情を言語化して、悲しい感情への共感を伝えてください。単に感情を言語化するだけではなく、相手の考えを理解できるように努めることも大切です。
気持ちの共感ができると、認知症の家族との信頼関係を築きやすくなり、介護をスムーズに行えるようになります。
2-4.妄想は否定せず原因を探る
認知症になると、「誰かに物を盗られた」「夫が浮気をしている」などの妄想を抱き、真実だと信じ込んでしまうことがあります。認知症患者が語る妄想を聞いて、つい否定したくなる人は多いでしょう。
しかし、妄想を信じ込んでいる本人にとっては妄想こそが真実です。もしも家族が妄想を否定してしまえば、認知症患者は混乱して、家族のほうが嘘をついていると妄想を重ねてしまうかもしれません。
認知症の症状で起こる妄想は否定せず、原因を探ることが重要です。何が妄想の原因になったかを理解すると、相手の妄想を助長せず、穏やかに収める方法を見つけられます。
2-5.よい感情が残るよう前向きな言葉をかける
認知症患者は症状が進行するうちに、自分が体験した内容を忘れてしまいます。
しかし、体験を通して得られた感情は、体験自体を忘れた後でも覚えていることがあります。認知症介護をする家族は、高圧的な口調・態度はせず、本人の記憶によい感情が残るよう前向きな言葉をかけることが大切です。
たとえば認知症の家族が食事をうまくできたときは、「がんばったね」「きれいに食べられたね」と声かけしましょう。できたことを忘れてしまっても、褒められて嬉しくなった感情は残り、次に食事をするときのモチベーションとなる可能性があります。
3.認知症介護をする家族の心の負担を軽減する方法

認知症の家族を不安にさせまいと明るく振る舞っていても、心が疲弊することはあります。
介護者自身が心を病まないように、心の負担を軽減する方法を知っておきましょう。
がんばりすぎない
認知症介護をする家族は、認知症の家族に元気なままでいてほしいという願いを持ち、がんばりすぎてしまう傾向があります。しかし、がんばる姿勢を長く続けていては心と身体が持ちません。
認知症は完治が難しく、介護状況は長期にわたります。認知症の家族と、介護をする自分自身が長く元気でいるためにも、がんばりすぎないようにしましょう。
1人で抱え込まない
認知症介護をする上では、「家族の面倒は自分がすべて見なければ」と1人で抱え込まないことが大切です。認知症患者の介護を1人ですべて行うことは身体的・精神的負担が大きく、介護疲れによってうつ状態になる可能性もあります。
認知症介護は自分1人ですべてやろうとせず、生活支援に代表される福祉・介護サービスの利用がおすすめです。介護負担を減らすことで心が軽くなり、毎日を前向きに過ごせます。
周りと比べない
認知症と一口に言ってもさまざまな種類があり、症状が進行する早さは人によって異なります。認知症の進行は、介護者の接し方や介護環境とは無関係であるため、周りと比べないようにしましょう。
家庭で行う認知症介護は、家族ごとに合った形があります。周りと比べるよりも、自分たちに合った介護の形を考えることが大切です。
愚痴や弱音を溜め込まない
認知症介護を行う中では、自分の思い通りにいかない状況がどうしても出てきます。愚痴や弱音は溜め込まずに、適切に吐き出す機会を作ることが大切です。
愚痴や弱音を吐き出すと、自分がどれだけ介護ストレスを感じているかに気付くことができます。悩みを相談できる友人や、認知症の家族介護者が集まる家族会など、愚痴や弱音を吐き出せる先を用意しておくことがおすすめです。
終わりがないと思わない
認知症介護に疲れ、「いつまでも今の状態が続くのだろうか」と考える人は多いでしょう。しかし、認知症で起こり得るさまざまな症状は、症状が進行することでいつか必ず終わりが来ます。
認知症患者が行う徘徊や妄想に困っていても、本人の身体機能や脳の機能が低下するにつれて、症状は出なくなります。認知症介護には終わりがないとは思わず、認知症の家族と穏やかに過ごせる時間を多く取りましょう。
まとめ
家族が認知症になったとき、否定的な感情を持つことは当然の反応です。今は戸惑いや混乱を感じていても、いつかは認知症を受容できる時期が来ると胸に留めておいてください。
実際の介護を行うときは、相手の感情や考えを尊重することが大切です。紹介した「5つの原則」を押さえて、認知症の家族と明るく過ごせる介護を心がけましょう。
認知症介護には、いつか必ず終わりが来ます。認知症介護をする家族は、心の負担をなるべく軽減して、認知症の家族と過ごす今の時間を大切にしてください。
認知症に向き合う家族や専門職員の方にお届けする。認知症10,000人の方と関わる私たちが実践する、穏やかな気持ちで向き合うケア手法とは?