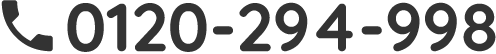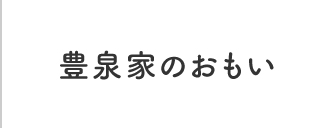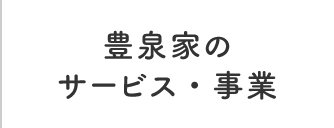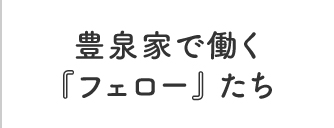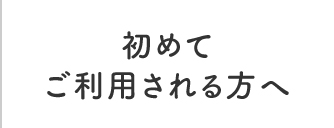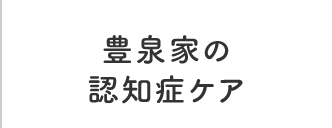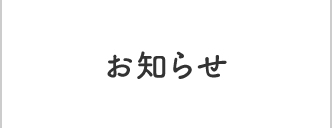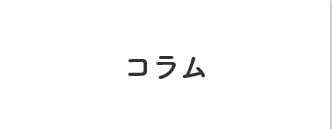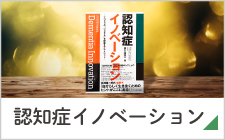認知症とは?主な症状や治療法・もの忘れとの違い
2023.05.25
認知症ケア
認知症とは?主な症状や治療法・もの忘れとの違い
認知症とは?主な症状や治療法・もの忘れとの違い
人は年齢を重ねるにつれて、もの忘れや判断力の低下が起こるようになります。しかし、もの忘れが激しくなったり、自分で生活管理ができなくなったりすると、認知症の可能性を考える人は多いのではないでしょうか。
家族や自分自身が認知症かもしれないと思ったときは、認知症の症状を理解して、どのような治療法や予防法があるかも知っておくことが重要です。当記事では認知症とは何かから、具体的な症状やもの忘れとの違い、認知症予防のポイントまでを解説します。
認知症に向き合う家族や専門職員の方にお届けする。認知症10,000人の方と関わる私たちが実践する、穏やかな気持ちで向き合うケア手法とは?
目次
- 1.認知症とは?
- 1-1.認知症の主な種類と治療法
- 2.認知症に多い症状
- 2-1.中核症状
- 2-2.BPSD
- 3.認知症ともの忘れの違い
- 4.認知症を予防するには?
- まとめ
1.認知症とは?

認知症とは、さまざまな原因により脳の認知能力に問題が生じて、記憶・判断力などが低下している状態のことです。記憶・判断力は生活能力や社会活動と深く結びついており、認知症になると日常生活や対人関係に支障をきたします。
日本において認知症を発症している人の数は、2012年時点で約462万人です。高齢者(65歳以上)のうち約7人に1人が認知症を発症しており、2025年には700万人(約5人に1人)に増加すると言われています。
日本は超高齢社会であり、認知症になる人は今後も増えることが予測されます。認知症は年齢を重ねると誰でもなり得るため、認知症についての理解を深め、認知症の人と共生できるようにすることが重要です。
(出典:知ることから始めよう みんなのメンタルヘルス「認知症」
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=WwE9LLpYbVZTIDMI)
出典:政府広報オンライン「もし、家族や自分が認知症になったら 知っておきたい認知症のキホン」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201308/1.html)
(出典:厚生労働省「認知症の人の将来推計について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000524702.pdf)
1-1. 認知症の主な種類と治療法
認知症は発症する原因や発生する症状によって、主に下記の4種類に分けられます。
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は、脳神経の変性により脳の一部が萎縮する過程で起こるとされている認知症です。認知症の中で最も多いパターンであり、認知症全体の約50%を占めます。アルツハイマー型認知症の初期症状は記憶障害で始まるケースが多く、忘れていることに対する「取り繕い」も主な症状として挙げられます。
血管性認知症
血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害が原因となって起こるとされている認知症です。認知症の中ではアルツハイマー型認知症に次いで多く、認知症全体の約15%を占めます。血管性認知症の症状は脳記憶障害や言語障害が多く、症状が突然現れたり、段階的に悪化・変動したりすることが特徴です。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は、脳の神経系にレビー小体と呼ばれる異常なたんぱく質ができることで起こるとされている認知症です。脳幹にレビー小体ができるパーキンソン病と近い関係性にあり、認知症全体の約15%を占めます。レビー小体型認知症の主な症状はパーキンソン症状と呼ばれる筋肉のこわばりや震え、認知機能の低下、幻視などです
前頭側頭型認知症
前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉や側頭葉に病変ができることで起こるとされている認知症です。病変により前頭葉が障害された場合は、自分を抑えられず衝動的な行動を取るなど、人格・行動の変化が見られるとされています。対して側頭葉が障害された場合は、発話が困難になったり、言語の理解が失われたりするなどの言語障害が主な症状です。
上記4つのうち、アルツハイマー型認知症・レビー小体型認知症・前頭側頭型認知症の3つは「変性性認知症」に含まれます。変性性認知症とは、特定の神経細胞群が徐々に減少する認知症のことです。変性性認知症や血管性認知症は完治が難しく、症状の進行を遅らせる治療法が取られています。
(出典:知ることから始めよう みんなのメンタルヘルス「認知症」
/https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=WwE9LLpYbVZTIDMI)
(出典:政府広報オンライン「もし、家族や自分が認知症になったら 知っておきたい認知症のキホン」
/https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201308/1.html)
(出典:厚生労働省 四国厚生支局「認知症の基礎知識と対応について」
/https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/chiiki_houkatsu/000086447.pdf)
(出典:独立行政法人国立病院機構 宇多野病院「レビー小体型認知症(DLB)」
/https://utano.hosp.go.jp/outpatient/other_know_neurology_04.html)
2. 認知症に多い症状

認知症の症状は、「中核症状」と「BPSD」の2つに分けられます。認知症の人と共生する上では、認知症が記憶面だけでなく、心理面にも大きく影響することを理解しなければなりません。
ここでは中核症状とBPSDについて、症状が出る原因や具体的な症状を解説します。
2-1.中核症状
中核症状とは、脳の神経細胞が減少することで起こる、認知症の直接的な症状です。
中核症状の具体的な5つの症状と、症状の例を紹介します。
記憶障害
記憶障害は、直前のことを思い出せなくなったり、以前は覚えていたはずの記憶を忘れたりする症状です。
<記憶障害の例>
- ● 数分前にした会話を忘れる
- ● よく会っている人の名前が思い出せない
見当識障害
記見当識障害は、月日・時間・場所などの「自分が置かれている状況」に関わる情報が理解できなくなる症状です。
<見当識障害の例>
- ● 今日の曜日が分からない
- ● 自宅の近所で迷子になる
理解・判断力の障害
理解・判断力の障害は、物事の正しい理解や、状況に応じた判断ができなくなる症状です。
<理解・判断力の障害の例>
- ● 新聞を見ても何が書かれているか分からない
- ● お金の計算ができない
実行機能障害
実行機能障害は、計画を立てて順序よく物事を進めることができなくなる症状です。
<実行機能障害の例>
- ● 料理を段取りよく作れなくなる
- ● 着衣や入浴ができなくなる
感情表現の変化
感情表現の変化は、自分や周囲の状況に対して適切な感情表現ができなくなる症状です。
<感情表現の変化の例>
- ● いきなり怒り出したり、泣いたりする
- ● 周囲に対して無関心になる
(出典:知ることから始めよう みんなのメンタルヘルス「認知症」
/https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_recog.html)
出典:政府広報オンライン「もし、家族や自分が認知症になったら 知っておきたい認知症のキホン」
/https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201308/1.html)
2-2.BPSD
BPSDは、認知症の行動・心理症状を意味する「Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia」の略語です。
認知症の中核症状が、本人の性格や周囲の環境・人間関係へ影響を及ぼし、さまざまな行動・心理症状を起こします。
BPSDの主な症状は、不安や焦燥を感じる、うつ状態になる、徘徊する、幻覚・妄想を見るなどです。具体的な例を2つ紹介します。
<BPSDの例>
- ● 持っていた趣味に関心を持たなくなる
- ● 亡くなった家族と暮らしていると主張する
(出典:知ることから始めよう みんなのメンタルヘルス「認知症」
/https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_recog.html)
出典:政府広報オンライン「もし、家族や自分が認知症になったら 知っておきたい認知症のキホン」
/https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201308/1.html)
3. 認知症ともの忘れの違い

認知症と間違われやすい症状に、「もの忘れ」があります。もの忘れとは、記憶力の低下によって覚えていたことを思い出せない、もしくは思い出すまでに時間がかかる状態のことです。
認知症ともの忘れは、どちらも年齢を重ねるほどに起こりやすい傾向があります。また、認知症の中核症状に「記憶障害」があるように、認知症ともの忘れは症状もよく似ていることが特徴です。
しかし、認知症ともの忘れには、いくつかのポイントで違いがあります。
まず、もの忘れの原因は加齢に伴う記憶力の低下です。脳の神経細胞に異常が生じることで症状が起こる認知症に対し、加齢によるもの忘れは誰にでも起こり得ます。
さらに、認知症と加齢によるもの忘れでは、覚えていたことの忘れ方やもの忘れの自覚、日常生活への支障などが異なります。
具体的な違いは、下記の表を参考にしてください。
| 加齢によるもの忘れ | 認知症によるもの忘れ | |
|---|---|---|
| 体験したこと | 一部を忘れる 例)朝ごはんのメニュー |
すべてを忘れている 例)朝ごはんを食べたこと自体 |
| もの忘れの自覚 | ある | ない |
| 探し物に対して | (自分で)努力して見つけようとする | 誰かが盗ったなどと、他人のせいにすることがある |
| 日常生活への支障 | ない | ある |
| 症状の進行 | 極めて徐々にしか進行しない | 進行する |
(引用:政府広報オンライン「もし、家族や自分が認知症になったら 知っておきたい認知症のキホン」
/https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201308/1.html/
引用日/2022/02/11)
経験したことの一部だけを忘れていたり、忘れることが多くなっても日常生活への支障がなかったりする場合は、加齢によるもの忘れの可能性が高いと言えます。
一方で、経験したこと自体を忘れたり、忘れている自覚もなくなったりする場合は、認知症によるもの忘れの可能性が高いと言えるでしょう。
(出典:知ることから始めよう みんなのメンタルヘルス「認知症」
/https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_recog.html)
出典:政府広報オンライン「もし、家族や自分が認知症になったら 知っておきたい認知症のキホン」
/https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201308/1.html)
4.認知症を予防するには?
認知症を予防するには、「軽度認知障害(MCI)」のうちに早期対応することが重要です。
軽度認知障害(MCI)とは、もの忘れなどの症状があるものの、認知症とは診断されない状態のことです。軽度認知障害(MCI)の人は、約半数が5年以内に認知症に移行すると言われています。
軽度認知障害(MCI)の特徴は、下記の3つです。
- ● もの忘れなどの認知機能低下が見られる
- ● 本人にもの忘れが多い自覚がある
- ● 日常生活全般への大きな支障はない
軽度認知障害(MCI)のうちに予防を開始すると、認知症の進行を遅らせることが期待できます。もの忘れが増えたと思い始めたときは、認知症医療を扱う専門医への受診・相談を検討してください。
(出典:知ることから始めよう みんなのメンタルヘルス「認知症」
/https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_recog.html)
まとめ
認知症は記憶・判断力などが低下して、日常生活や対人関係に支障をきたす状態です。記憶障害や見当識障害に代表される中核症状や、BPSDに該当する行動・心理症状が見られたときは、認知症の可能性があります。
認知症の中で多数を占める変性性認知症は、完治が難しいとされています。認知症を予防するためには症状の早期発見・早期対応を取るようにしてください。
自分や家族のもの忘れが増えたと思ったときは、専門医を受診することがおすすめです。
認知症に向き合う家族や専門職員の方にお届けする。認知症10,000人の方と関わる私たちが実践する、穏やかな気持ちで向き合うケア手法とは?